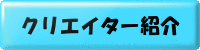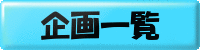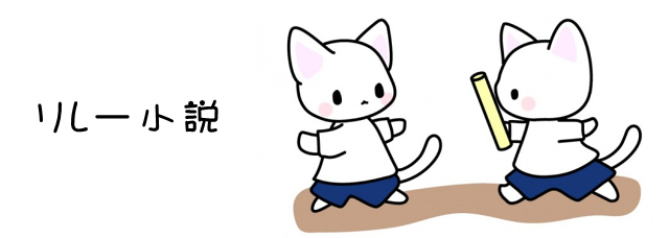
『タイトル未定』
第3話
隣国の城下町のはずれ、少し寂れた場所に1つだけ佇む屋敷があった。
辺りに建つ家よりは一回りも二回りも大きなその家は一目で師匠の妹の家だとわかった。
夜通し山の中を歩いて来たのだが、気付けばもう日が高くまで昇っていた。
僕は山歩きで汚れた身なりを整えると玄関口で呼び鈴を鳴らした。
チリンチリン
上品な音が辺りに響く。しかし屋敷からは何の反応もない。
もしかして留守なのだろうか。そう思い踵を返そうとした時、後ろから声を掛けられた。
「師匠に何か御用でしょうか。」
見ると僕よりも一回り大きながたいの良い男が何やら大きな荷物を抱えて立っていた。
何より驚いたのは男の瞳だ。右目がは燃えるような赤色
左目は吸い込まれるような青色をしていた。
左右で目の色が違う人などこれまで見たことがなかった。
それは彼も同じだったようで、黒い瞳を持つ僕を訝し気に見つめてくる。
質問に答えなければ。僕は咄嗟に口を開いた。
「この屋敷の主人の兄の弟子です。師匠に言われて、師匠の妹さんを頼るべく参りました。」
言い終わって気が付いた、かなり怪しい自己紹介だったと思う。
しかし男は何か知っていたようで合点のいったような顔をした後に
「あなたが師匠のお兄様のお弟子さんでしたか。
お話しは兼ねてより聞いています。さあ中へどうぞ。」
と、すんなりと中へ案内してくれた。
玄関を入ると大きなホールになっており、左右には2階へあがるための階段
真ん中は奥へと廊下が伸びている。
廊下は長すぎて奥の方は暗くなって見えない。外から見た以上に広い屋敷のようだ。
「師匠!戻りました!師匠のお兄様のお弟子さんがお見えです!」
男は玄関をくぐるやいなや、はち切れんばかりの大声でそう言った。
しかし返事はない。
「あの、やはり妹さんはお留守なのでしょうか。」
僕は不安になり、男にそう聞く。
男は少し眉間に皺を寄せながら呟く。
「あの人はまた潰れてるな。」
そう言うとスタスタと廊下の奥へと歩み始めた。僕は仕方なく男へ付いて行った。
ほどなく歩くと廊下の突き当りに辿り着いた。
そこには大きな両開きの扉が取り付けられていた。
男は勢いよくその扉を開け放つ。
「やっぱり!師匠、昼から飲んじゃ駄目っていつも言ってるじゃないですか。」
そこには空の瓶に囲まれた華奢な女性が机に突っ伏していたのだった。
「あー、お前か。水…水をくれ。」
男から師匠と呼ばれたその女性は首だけこちらにあげて
僕たちのことを視認するとすぐに水を求めた。
「まったく…どれだけ飲んだんですか。」
男は悪態を付きながら窓辺の炊事場まで歩いていく。
「んー、お前は…。」
ここでようやく女性は僕の存在に気付いたようだった。
男が女性の横に水の入ったコップを置きながら答える。
「師匠のお兄様のお弟子様みたいです。」
そこでようやく女性は上体を起こし水を一気に飲み干した。
「そうか、お前がここに来たということは、あのクソ兄貴に何かあったってことか。」
「師匠は僕を守って死にました。」
僕は冷静にそう答える。しかし何がおかしかったのか女性は大笑いを始めた。
「死んだ?あの兄貴が?アイツは殺したって死にやしないよ。」
しかし、それには僕も少し強めに反論する。
「死んだんです。勇者が現れて、それで僕を守って…。
僕がこの手で師匠を弔いました。間違いないです。」
そこまで言っても女性はまだ笑い足りないのか口元に手をあてクククと笑いながら続ける。
「ああ、わかった。それで私のとこに来たってんだね、魔王クン。」
僕は突然、魔王と呼ばれたことに驚いた。
何か言わねばと思うのだが言葉が口から出てこない。
いろいろな思考が次々と頭に流れ込んで1つも言葉にならない。
「兄貴はどう思ってんのか知らないけどね、私は君が魔王で間違いないと思っているよ。」
たじろいでいる僕を見てなお女性は言葉を紡ぎ続ける。
その言葉の1つ1つが僕の胸に深く突き刺さるような感じがした。
「まずは君自身が自分がどういう存在なのかを知らなければね。」
そこで女性は隅で話が終わるのを待っていた男を指さす。
「アイツは私の弟子なんだが、君、アイツと会った時に何か違和感は感じなかったかい?」
違和感、と言っていいのだろうか。確かに僕は彼とさっき会った時に
左右で違う目の色の人には今まで会ったことがないとは思った。
僕はそのことを正直に告げる。
「そう、左右で違う目の色を持つ人間なんて、この世でもコイツくらいのもんだろう。」
そこで女性はニヤリと笑みを浮かべる。
「では何故、左右で目の色が違うかわかるかい?」
左右で目の色が違う理由。目の色は生まれてくる魂がどの精霊の祝福を受けたかで決まる。
と、いうことはまさか…
「2つの精霊の祝福を受けて生まれたということですか?」
「ほう、わりかし頭の回転は良いほうだね。だが正解ではない。惜しいがね。」
そう言うと女性は立ち上がった。足元は覚束ないが机の周りをぐるぐると歩き出す。
「1つの魂に祝福は1つ。これは絶対だ。」
「では何故、彼は左右で目の色が違うのですか?」
「何、答えは簡単だよ。単純と言ってもいい。コイツの体には2つの魂が宿っているのさ。」
2つの魂が?そんなことが可能なのだろうか。
「そして2つの魂が宿っているから2種類の魔法が使える。こいつの場合は炎系と水系だね。」
そこで女性は再び席へと戻った。
「だがコイツはそのことを知らなかったから、私に出会うまで魔法が使えなかったんだ。」
そして僕を見る。
「君はあの頃のコイツとよく似ているよ。」
僕に何か知らないことがると伝えたいのだろうか。そう言われると知らないことの方が多すぎるくらいだと自分でも自覚しているのだが。
「まあ習うより慣れろだ。外に出てコイツと闘ってみな。そしたらお前の力も見えてくるだろうよ。」
そう言うと女性は弟子の男に2,3指示を出すと、覚束ない足取りで外へと出ていった。
「さあ私たちも行きましょう。」
弟子の男もそういうと外へ出ていく。
これからあの男と闘うのか?
僕は何がなにやらわからずに2人の後を追うのだった。
担当:会長(ティンカ代理)
<<前のページ 次のページ>>