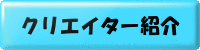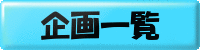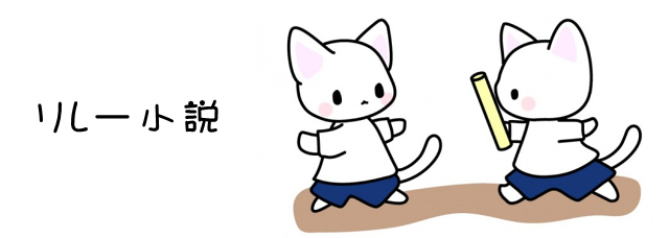
『タイトル未定』
第16話
その闘技場は特別目立った装飾がされているわけではない。直径50mくらいであろう円形の壁の内側にだだっ広い空間が広がり、その壁を囲うように1段上げられた観客席が申し訳程度に備えつけられているだけのシンプルで素朴な建物であった。
だが、それ故にシトリー達は思わず息を飲んだ。
シンプルであるがために目の前に広がる空間が、ただただ闘うためだけに切り取られた空間だということが肌で感じ取れたからだ。
ここに何人もの闘気を帯びた猛者が集い、血を流し、命を落としたのだということが容易に想像できた。そしてその魂をこの建物が全て吸い取っているようにも感じた。
「これは・・・すげぇな・・・。」
最初に口を開いたのはシトリーだった。
「自分の中に眠ってた闘志が嫌でも呼び覚まされるっつーか・・・よくわかんねぇけど身体の奥底がすげー熱くなってきやがる。」
一同も同じ感覚だったようで、神妙な面持ちで頷く。
「さて、では此度の闘いのルールを発表しましょう。」
そんな中、表情1つ変えずにカンナが口を開いた。
「と、言っても闘い自体にルールは無いと言っても良いでしょうね。なんでも有り、相手が死ぬか戦闘不能に陥った場合のみ勝敗が決します。こちらからはサブナック卿とオセ卿の2人、そちらはお兄様以外の不躾な犬3匹、1対1の勝ち抜き戦でいかがでしょうか?」
「おいおい、3対2ってこっちの方が有利じゃねぇか?私らもえらく舐められたもんだな?あぁ?」
シトリーがカンナに食って掛かろうとするのをフルカスが必死に止める。
「師匠、こっちが有利なんだからいいじゃないですか。余計なことを言わないで下さい!」
その様子を見て、カンナは口元に手をやり上品に笑った。
「フフ。これだから馬鹿は見てて飽きませんわね。」
「ああん?」
フルカスを振り払おうとするシトリーにより一層力が入る。
「ちょっ!! ダンタリオンさん、見てないで手伝って!!」
「いや、俺は闘う前から死にたくはないからね。」
「この闘いの目的は勝ち負けを決することではありません。あなた方に私達地下勢力が付き従うだけの価値があるかどうか見極めるための闘いです。サブナック卿とオセ卿は地下勢力の中でも突出した戦闘能力を誇ります。この2人をもってして勝てないのであれば、私達はあなたに付き従う以外に道はないということです。・・・まあ万が一にもそこの汚らしい雌犬などに負けるようなことはないでしょうけど。」
このカンナの言葉が聞き終わるか終わらないかのところで、シトリーはフルカスの制止を振り切り一瞬のうちにカンナとの間合いを詰める。そして詠唱をすることなく掌から水の波動をカンナに向けて打ち出した。僅か一瞬の出来事。常人であれば視認することすらできなかったであろう。
しかし、シトリーの打ち出した水砲はカンナを捉えることなく空を切り、あろうことかカンナはシトリーの背後に立っていたのだった。
「詠唱もせずにそれだけの水砲を打ち出せるのはたいしたものですね。でも足りない。それだけでは私には到底届きませんわ。」
言うとカンナは左足を軸に右足を大きく振り上げ、シトリー目指して振り下ろす。その足先はカンナの瞳と同様に真っ赤な炎に包まれていた。
一部始終を見ていたフルカスとフォルネウスはシトリーを庇うべく走りだした。しかしカンナのあまりの速さにあと一歩届かない。このままではシトリーはカンナの一発をもろに喰らってしまう。その場にいた全員が息を飲んだ。
「・・・あら、そちらにも少しはできる方がおられますのね。」
シトリーに向けてに振り下ろされた一閃は、いつの間にかシトリーとカンナの間に割って入ったダンタリオンによって防がれていた。
「しかもよく見れば先々代の腑抜けた魔王様をたぶらかした先々代の勇者様ではないですか。」
「これは、これは、こんな地下帝国にまで名が知れ渡ってるとは俺も結構有名になったものですね。」
言うとダンタリオンはシトリーの方に目をやる。
「ったく、お前は昔から全く進歩してないな。キレたら考え無しに突っ込みやがる。怒りに任せた魔法の出力は随一だが、彼我の戦力差くらい考慮して闘わないと今みたいなことになるぞ。」
「うっせー、クソ兄貴。お前がいなくても私は今の攻撃くらい防げた。」
「はいはい、わかったから、とりあえず下がるぞ。まだ試合は始まってもいないんだ。」
言うとダンタリオンは拗ねて座り込むシトリーを強引に引きずりながら自陣へと帰る。それを見てカンナもサブナック卿とオセ卿を引きつれ、ダンタリオンとは逆方向にある自陣へと向かった。
「まずはオセ卿、あなたが行って下さい。あなたの実力であれば、一人で三連勝も容易いでしょう。しかし・・・」
そう言ってカンナは自身の左肩を抑える。
「シトリーとかいう女の魔法出力、あれには気を付けた方がいいですわね。水砲にはかすりもしていないのに、圧だけで左腕に少々ダメージを負ってしまいましたわ。」
「なに、向こうが魔法を放つ前に勝敗を決せばいいだけのこと、ご心配には及びません。」
オセ卿は静かにそう呟くとカンナ達に背を向け闘技場へ向かった。
「おや、あの馬鹿力の女か、元勇者様が出て来るかと思えば、あなたが最初の相手ですか。いわゆる当て馬というやつですかね。」
シトリー達はまずフルカスを闘技場に立たせたようだ。
「お前ごときに師匠の手を煩わせるまでもない。」
売り言葉に買い言葉。闘技場は異様な雰囲気に包まれていた。正に一触即発とはこの状態のことを言うのであろう。一瞬あたりが静寂に包まれる。2人の集中力が極限まで高まったその瞬間、試合開始のゴングが闘技場内に鳴り響いた。
「我は願う水よ・・・」
早速フルカスが詠唱を始める。しかし、次の瞬間フルカスは地面に叩きつけられていた。
「遅い。」
一瞬でフルカスとの間合いを詰め、更には足払いによってフルカスの自由を奪う。全く魔法に頼らない戦術をとってくるオセ卿は、魔法対魔法の戦闘しか経験のないフルカスにとってはとてもやりにくい相手だった。
「魔法はとても便利ですし、破壊力もあります。一見万能のように思えますが唯一の欠点がスピードの遅さです。強力な魔法を放とうとすると詠唱がいる。詠唱を伴わない魔法でも魔力の変換から出力までに若干タイムラグがある。」
言いながらオセ卿は目にも止まらぬ速さで次々に拳や蹴りを、何とか立ち上がったフルカスに叩きこんでいる。
「私は生まれつき魔力がほとんど無かった。だから魔法の欠点をついた闘い方ができるように徹底的にスピードを鍛え上げました。・・・魔法で私に勝つのは不可能ですよ。」
フルカスは最早立っているのがやっとの状態。しかしオセ卿はその手をゆるめない。
そして、開始から1分も経たないうちに、フルカスは気を失いその場に倒れ込んでしまった。
「ふん。口ほどにもありませんね。まあ私の連撃を受けてまだ生きているだけでも称賛に値しますよ。さあ、次は誰ですか?こんなくだらない茶番は早く終わらせましょう。」
その言葉に立ち上がったのはシトリーだった。それをダンタリオンが慌てて止めに入る。
「待て、弟子をやられて憤るのはわかるが、今の興奮状態のお前じゃあいつには・・・」
そこまで言い掛けてダンタリオンはあまりの寒気に声が出なくなった。実妹であるが、こんな目をしたところを一度も見たことがない。刺さるような殺気を隠そうともせず、しかし怒りに我を忘れることもなくただただ静かに目の前のダンタリオンを避けてシトリーは静かに呟いた。
「なんだろうねこの気持ちは。弟子をボコボコにされたってのにひどく落ち着いてやがる。まるで夜中の湖のように波一つ立っていない。なのにそれと同時に今すぐあのオセとやらを地獄の底へぶち込みたい気分なんだよ。」
だが、それ故にシトリー達は思わず息を飲んだ。
シンプルであるがために目の前に広がる空間が、ただただ闘うためだけに切り取られた空間だということが肌で感じ取れたからだ。
ここに何人もの闘気を帯びた猛者が集い、血を流し、命を落としたのだということが容易に想像できた。そしてその魂をこの建物が全て吸い取っているようにも感じた。
「これは・・・すげぇな・・・。」
最初に口を開いたのはシトリーだった。
「自分の中に眠ってた闘志が嫌でも呼び覚まされるっつーか・・・よくわかんねぇけど身体の奥底がすげー熱くなってきやがる。」
一同も同じ感覚だったようで、神妙な面持ちで頷く。
「さて、では此度の闘いのルールを発表しましょう。」
そんな中、表情1つ変えずにカンナが口を開いた。
「と、言っても闘い自体にルールは無いと言っても良いでしょうね。なんでも有り、相手が死ぬか戦闘不能に陥った場合のみ勝敗が決します。こちらからはサブナック卿とオセ卿の2人、そちらはお兄様以外の不躾な犬3匹、1対1の勝ち抜き戦でいかがでしょうか?」
「おいおい、3対2ってこっちの方が有利じゃねぇか?私らもえらく舐められたもんだな?あぁ?」
シトリーがカンナに食って掛かろうとするのをフルカスが必死に止める。
「師匠、こっちが有利なんだからいいじゃないですか。余計なことを言わないで下さい!」
その様子を見て、カンナは口元に手をやり上品に笑った。
「フフ。これだから馬鹿は見てて飽きませんわね。」
「ああん?」
フルカスを振り払おうとするシトリーにより一層力が入る。
「ちょっ!! ダンタリオンさん、見てないで手伝って!!」
「いや、俺は闘う前から死にたくはないからね。」
「この闘いの目的は勝ち負けを決することではありません。あなた方に私達地下勢力が付き従うだけの価値があるかどうか見極めるための闘いです。サブナック卿とオセ卿は地下勢力の中でも突出した戦闘能力を誇ります。この2人をもってして勝てないのであれば、私達はあなたに付き従う以外に道はないということです。・・・まあ万が一にもそこの汚らしい雌犬などに負けるようなことはないでしょうけど。」
このカンナの言葉が聞き終わるか終わらないかのところで、シトリーはフルカスの制止を振り切り一瞬のうちにカンナとの間合いを詰める。そして詠唱をすることなく掌から水の波動をカンナに向けて打ち出した。僅か一瞬の出来事。常人であれば視認することすらできなかったであろう。
しかし、シトリーの打ち出した水砲はカンナを捉えることなく空を切り、あろうことかカンナはシトリーの背後に立っていたのだった。
「詠唱もせずにそれだけの水砲を打ち出せるのはたいしたものですね。でも足りない。それだけでは私には到底届きませんわ。」
言うとカンナは左足を軸に右足を大きく振り上げ、シトリー目指して振り下ろす。その足先はカンナの瞳と同様に真っ赤な炎に包まれていた。
一部始終を見ていたフルカスとフォルネウスはシトリーを庇うべく走りだした。しかしカンナのあまりの速さにあと一歩届かない。このままではシトリーはカンナの一発をもろに喰らってしまう。その場にいた全員が息を飲んだ。
「・・・あら、そちらにも少しはできる方がおられますのね。」
シトリーに向けてに振り下ろされた一閃は、いつの間にかシトリーとカンナの間に割って入ったダンタリオンによって防がれていた。
「しかもよく見れば先々代の腑抜けた魔王様をたぶらかした先々代の勇者様ではないですか。」
「これは、これは、こんな地下帝国にまで名が知れ渡ってるとは俺も結構有名になったものですね。」
言うとダンタリオンはシトリーの方に目をやる。
「ったく、お前は昔から全く進歩してないな。キレたら考え無しに突っ込みやがる。怒りに任せた魔法の出力は随一だが、彼我の戦力差くらい考慮して闘わないと今みたいなことになるぞ。」
「うっせー、クソ兄貴。お前がいなくても私は今の攻撃くらい防げた。」
「はいはい、わかったから、とりあえず下がるぞ。まだ試合は始まってもいないんだ。」
言うとダンタリオンは拗ねて座り込むシトリーを強引に引きずりながら自陣へと帰る。それを見てカンナもサブナック卿とオセ卿を引きつれ、ダンタリオンとは逆方向にある自陣へと向かった。
「まずはオセ卿、あなたが行って下さい。あなたの実力であれば、一人で三連勝も容易いでしょう。しかし・・・」
そう言ってカンナは自身の左肩を抑える。
「シトリーとかいう女の魔法出力、あれには気を付けた方がいいですわね。水砲にはかすりもしていないのに、圧だけで左腕に少々ダメージを負ってしまいましたわ。」
「なに、向こうが魔法を放つ前に勝敗を決せばいいだけのこと、ご心配には及びません。」
オセ卿は静かにそう呟くとカンナ達に背を向け闘技場へ向かった。
「おや、あの馬鹿力の女か、元勇者様が出て来るかと思えば、あなたが最初の相手ですか。いわゆる当て馬というやつですかね。」
シトリー達はまずフルカスを闘技場に立たせたようだ。
「お前ごときに師匠の手を煩わせるまでもない。」
売り言葉に買い言葉。闘技場は異様な雰囲気に包まれていた。正に一触即発とはこの状態のことを言うのであろう。一瞬あたりが静寂に包まれる。2人の集中力が極限まで高まったその瞬間、試合開始のゴングが闘技場内に鳴り響いた。
「我は願う水よ・・・」
早速フルカスが詠唱を始める。しかし、次の瞬間フルカスは地面に叩きつけられていた。
「遅い。」
一瞬でフルカスとの間合いを詰め、更には足払いによってフルカスの自由を奪う。全く魔法に頼らない戦術をとってくるオセ卿は、魔法対魔法の戦闘しか経験のないフルカスにとってはとてもやりにくい相手だった。
「魔法はとても便利ですし、破壊力もあります。一見万能のように思えますが唯一の欠点がスピードの遅さです。強力な魔法を放とうとすると詠唱がいる。詠唱を伴わない魔法でも魔力の変換から出力までに若干タイムラグがある。」
言いながらオセ卿は目にも止まらぬ速さで次々に拳や蹴りを、何とか立ち上がったフルカスに叩きこんでいる。
「私は生まれつき魔力がほとんど無かった。だから魔法の欠点をついた闘い方ができるように徹底的にスピードを鍛え上げました。・・・魔法で私に勝つのは不可能ですよ。」
フルカスは最早立っているのがやっとの状態。しかしオセ卿はその手をゆるめない。
そして、開始から1分も経たないうちに、フルカスは気を失いその場に倒れ込んでしまった。
「ふん。口ほどにもありませんね。まあ私の連撃を受けてまだ生きているだけでも称賛に値しますよ。さあ、次は誰ですか?こんなくだらない茶番は早く終わらせましょう。」
その言葉に立ち上がったのはシトリーだった。それをダンタリオンが慌てて止めに入る。
「待て、弟子をやられて憤るのはわかるが、今の興奮状態のお前じゃあいつには・・・」
そこまで言い掛けてダンタリオンはあまりの寒気に声が出なくなった。実妹であるが、こんな目をしたところを一度も見たことがない。刺さるような殺気を隠そうともせず、しかし怒りに我を忘れることもなくただただ静かに目の前のダンタリオンを避けてシトリーは静かに呟いた。
「なんだろうねこの気持ちは。弟子をボコボコにされたってのにひどく落ち着いてやがる。まるで夜中の湖のように波一つ立っていない。なのにそれと同時に今すぐあのオセとやらを地獄の底へぶち込みたい気分なんだよ。」
担当:会長
<<前のページ 次のページ>>