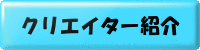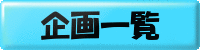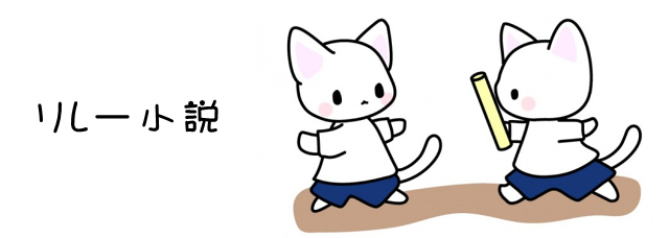
『タイトル未定』
第13話
「どうすんだよコレ、どうなるんだよコレ」
赤子が姿を消して翌朝、ベリトの邸宅内の応接間。
高貴を通り越してやたらと悪趣味な真紅のソファに幅をきかせながら、人間の女がうめく。
弟子がその隣…といっても女のせいで随分窮屈そうにちょこんと座る。
ムルムルとフルフルといったか…魔族のメイド達は忙しなく、女のグラスにワインを注ぎ、ぱたぱたと料理を運んでいた。
向かいのソファでは、フォルネウスが頭を抱えていた。
魔族でも指折りの実力者…衣類の上からでも鍛え上げられた太腿が分かる。
そしてその強靭な太腿を枕にし、ご満悦の表情で女の方に顔を向けている魔族が、この屋敷の主人ベリトである。
もはやボディタッチという領域でも無いのだが、音に聞こえし魔族の剣帝様は余程余裕が無いらしい。
「簡単に魔王が奪還されちまった。サッカーボールじゃねーんだぞ」
女が顔を真っ赤にして問い詰めてくる。
これは怒りによるものなのか、既に3瓶目が尽きようとしているワインによるものなのか。
立場上彼女らは魔王の護衛という形で依頼継続、何やら責められているフォルネウスは依頼者ということになるのだが…まあ任命責任というやつだろう。
なんとか気を持ち直し、彼女らの方を向いた。
「割と確信に近い予測なのですが、いいですか」
女がフォルネウスを顎で指す。
「なんだよフォルたん、言ってみろ」
「フォルたんはやめて下さい」
フォルネウスは咳払いをし、続けた。
「まず、精神結界を抜けられる可能性は4つに絞られます。一つが精神干渉に抗える人間。ざっくりと言えば精神力が凄まじい人間と言いますか…ただし、そんな人間はまず居ません。少なくとも私の生きてきた300年、そのような人間は一人として居なかった。歴代勇者とて、決死の覚悟で不死山越えを選択した程ですから」
フォルネウスは更に続ける。
「次に我々のように、この精神結界の干渉を『それほど』受けない者達。これも私やベリトを含め、魔族の中でも極少数に限られます。結界を抜けるための数十メートルを歩いている間に、ムルムルとフルフルに捕捉されていたことでしょう。…そうなると考えられるのは残りの2つです」
女が何かに気付き、身を乗り出した。
「…まさか」
「3つ目はこの結界を張った張本人。最後に…結界を張った張本人と精霊の加護を同じくする者。つまり先々代、そして先代の魔王様」
精神結界は四大精霊の魔力を混ぜ合わせたもの。
つまり4人の術師で張るか、単独で全ての魔力を備える魔王にしか築くことは不可能。
もちろん女の弟子のように、複数の属性を兼ね備えるならば、術師の数はこの限りでは無いが。
対して、勇者特有の『光の魔法』は精霊の祝福とは全く似て非なるものである。
人々の間では『神々の祝福』であると言い伝えられているが...真偽は定かでは無い。
「ご名答だよ諸君」
空気を断つように、窓の外から声。
一同が一斉に顔を向けると、窓から白衣の男が覗き込んでいた。
「入れてくれないか、妹よ」
「何か言いたいならそこから話せ、もしくは昨日みたいに伝言役の泥人形でも飛ばしてきたらどうだ」
「道理で昨日取り押さえた時はあっけないと…」
どこか納得した様子のフルフルを横目で見やりながら、女が腕を組む。
「昔から土の魔法で比肩する者無しと言われた、兄貴の得意技だ。泥で自分そっくりに似せた人形を飛ばす。殺傷力は皆無だし一度に一体しか出せないが、情報伝達の手段としては申し分ない。先代魔王の面倒を見てた時期も、定期的に生活の様子を伝えに来てた。同時に憎まれ口も叩きやがるから、話を聞くたびにその場で粉々にしてやってたよ」
それを聞き、何かを悟るようにフォルネウスが口を開いた。
「そうか、あなたが先々代の勇者。そしてこの結界内まで泥人形を及ばせた魔力…どういった理屈かは判りかねるが、中に先々代魔王様が居らっしゃるのか」
「察しが良くて助かるよ。しかしどうしてそう思うんだい」
「恥ずかしながら魔王信仰者は一枚岩ではない。この場にいる我々のように玉座に魔王様すら居れば、それだけで平穏に大陸南部で暮らしていけると考えている者達だけでは無いのです。魔王城のある都市は帝都程ではありませんが、相当の規模があります。地下に住まう過激な魔族は、嬉々として勇者を打ち倒し、大陸北部の人間を蹂躙すべしと考えている」
「アタシもアイツら大嫌いなのよねン。ホントなら地下街ごと焼き尽くしちゃいたいくらい」
ベリトが口を挟むや、フォルネウスが制する。
「過去の魔王様達も同様の考えでした。人間憎しと考え、何度もその時代の勇者達と戦ってきた。しかし先々代の魔王様はその半ば因縁めいたものに疑問を感じていた。勇者との対話を望み、我らの制止も聞かず単身で不死山へと向かわれ...そして戻って来なかった。あの時は討たれたものかと思っていたが」
(神の意思に抗う魔王…だから俺は彼女に惹かれた)
うすら笑いを浮かべる神々を脳裏に想像しながら白衣の男、いや、その声色は『先々代の勇者』のそれと言うべきか…は続けた。
「俺と彼女はそれでも戦うことを避けられなかった。だから一つになった。さっき話に出た『過激派』の魔族の焚き付けがあったわけさ」
きりっとした瞳で、しかし膝枕からは決して頭を離さず、ベリトは窓の外に居るシリアスな不審者を見据えた。
「とりあえず『今』の話をしてくれるかしら。そしてこれからどうするか」
「そうだな、俺もしばらく君達に同行しようと考えている。さっき話に出てきていた結界を抜ける手段の4つ目…ご明察だ。昨夜帝都で皇帝が殺され、新たな皇帝に俺の弟子が収まった」
「! 蘇ったのか…」
4瓶目のワインを空けた女が口を開いた。
「この件については、道すがら話をしよう。とりあえず赤子はあいつの手のうちにある。思惑も多々あろうが、確実な目的が一つある。お前の首だ。あいつが生き返って皇帝を討っただけならハッピーエンドでも良かったんだが、その目的については俺の望むところじゃあ無い」
間髪入れず、白衣の男はフォルネウスに目を向けた。
「そこまで聞ければ、もう君も赤子に固執する必要は無いんだろう」
「その通りです。先代が光の魔法を失えば新たに生まれる勇者と違い、死すことで次が生まれる魔王が3人もこの世に居ることなど、今まで無かった。その誰かが南部を平定してくれるのならば、我らの目的はそれだけで良いのです」
ふむ、と白衣の男はうなずく。
「さて、次に目指す先は決まった。『魔王城都市』の深淵、地下街。どのみち魔族の意志を統一しなければ話にならない。フォルネウス、君も元々赤子を連れてそこを目指すつもりだったんだろう」
そこまで聞くや、ベリトが疑問を投げ掛ける。
「勇者様は地下の連中に恨みなんて無いの~ン?」
「一切無い…と言えば嘘になるが、そもそも恨みを晴らすことを『彼女』は望まない。活かすも殺すも相手の出方次第さ。必要とあらば玉座に座る覚悟もあるし、弟子や妹可愛さに帝国万歳となるかもしれない」
それを聞き、フォルネウスが力強く立ち上がる。
その勢いでベリトが力強く床に頭を打つ。
「そうと決まれば明朝にも発ちましょう。ベリト、ここを空けてもらうのも不安ではあるが、後々助けが必要となるかも知れない。便りは追って知らせる」
不死山を抜ければ魔王城が遠くうっすらと見える。
フォルネウス、先々代の勇者、その妹に弟子…4名は目的地へ目と鼻の先にまで迫っていた。
気だるそうに歩く女に歩調を合わせ、フォルネウスが話し掛けてくる。
「昨日の会話の中で確信したことがあります。あなた達は帝国の依頼で先代魔王を殺害した…しかし、別の思惑もあったのでしょう」
その通りだった。2種の精霊の力を宿す弟子を取り、魔力の判別にも自信はある。
そもそも実兄の中に魔王が宿っているなんてことは、薄々気づいていたことなのだ。
だからこそ、昨日の会話にさほどの驚きは無かった。
しかし兄が魔王を取り込んだにも関わらず、次の魔王は生まれてしまった。
もしそれが過去の魔王と同類なのだとしたら、兄の望み(の深い部分は分からないが)は露と消えてしまう。
かといって、兄が一度死んだあの時、復讐に身を焦がす不安定な魔王を抱え込む度量など、自分達には皆無だった。
ついでに金が入れば万々歳としていた事実も否定は出来ないが。
フォルネウスは続ける。
「そろそろ、皆さんのお名前を伺っても良いですか。勇者憎しの場に赴くのに肩書きのみだと不便そうだ」
女は一つ深呼吸を置き、頬を赤らめてボソッと呟いた。
「…シトリーだ。えらく乙女な名前だろう。弟子はフルカス、んでそこの宙を浮いてラクしてる糞兄貴が…」
「そうです、私が先々代勇者、ダンタリオンです」
ドヤ顔の元勇者を水弾で撃ち落とし、シトリーがフォルネウスに顔を向ける。
「これで隠し事はいよいよ無しだ、今後ともよろしく」
「ええ、よろしくお願いします。状況は決して芳しくないが、目的には確実に近付いている。あなた方にお願いして本当に良かった」
改めて言われた一言に、年甲斐も無く照れ臭そうに頭を掻く師匠。
それをニコニコ眺めていた弟子フルカスにも水弾が飛んできたのは、言うまでも無い。
担当:ミッキー
<<前のページ 次のページ>>